国民健康保険
ジェネリック医薬品を利用しましょう!
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造・販売される「先発医薬品と同等の効き目がある」と認められたものです。
ジェネリック医薬品は先発医薬品より安価のため、利用することで自己負担や医療費の節約につながります。ぜひジェネリック医薬品をご活用ください。
(注意)ジェネリック医薬品利用を希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。
国民健康保険
国民健康保険は、独自の収入に応じてお金を出し合い、病気やけがをした時等の医療費を負担する相互扶助の制度です。
勤務先の健康保険に加入している方やその被扶養者、生活保護を受けている方以外は加入しなければなりません。
ご注意ください!
加入の届け出が遅れると
加入の資格が発生した時点にさかのぼって保険税を納付しなければなりません。
また資格確認書等がないため、医療費は全額自己負担となります。
脱退の届け出が遅れると
国民健康保険の資格がなくなったあとに、国民健康保険で病院での診察等を受けた場合は、国民健康保険で負担した分の医療費を返還していただくことになります。
また、国民健康保険と社会保険の両方に保険税(料)を納めてしまうことがあります。
国民健康保険に加入されるかたについて
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などを辞めた人
- パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の人
加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です
国民健康保険では世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて加入などの届け出を行います。加入は世帯ごとですが、世帯の一人ひとりが被保険者です。
手続き
次のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
(注意)届け出には、世帯主と届出される方の個人番号(マイナンバー)カード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類を持参ください。
国民健康保険に加入する
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 上牧町に転入してきたとき | 住民異動届(写し) |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険の資格喪失証明書、離職票等 |
| 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者でなくなった日付のわかる証明書 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
| 子供が生まれたとき | 住民異動届(写し) |
| 外国籍の人が入るとき | 在留カード |
国民健康保険を脱退する
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 上牧町から転出するとき | 住民異動届(写し)、被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等) |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等) |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等) |
| 死亡したとき | 住民異動届(写し)、被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等)、会葬礼状または葬儀費用に関する領収書(喪主名の記載があるもの) |
| 外国籍の人が脱退するとき | 被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等)、在留カード |
その他の届
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
|
住民異動届(写し)、被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等) |
| 資格確認書等をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 本人確認書類のみ |
| 修学で長期間住所を離れるとき | 在学証明書、被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等) |
医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えたとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額の計算方法等が異なります。
(高額療養費の申請対象となった場合、診療月のおおよそ3か月後に対象世帯へお知らせを郵送します)
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
入院等により高額な診療を受けたとき、資格確認書等と一緒に「限度額適用認定証」等を提示すれば、同じ月内の医療機関等の窓口での支払いが限度額までとなります。
該当される人は事前に交付申請をしてください。
(マイナ保険証をご利用の場合、申請は不要です。)
申請が必要な人
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満で、所得区分が低所得者1・2もしくは現役並み所得者1・2の人
申請に必要なもの
- 交付を希望する人の被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等)
- 手続きする人の本人確認書類
- 世帯主と交付を希望する人のマイナンバー確認書類
自己負担額の計算方法
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ病院・診療所でも歯科は別計算、また外来・入院も別計算します。
- 入院した時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外となります。
70歳未満の人の自己負担限度額
| 区分 | 所得(注釈1)要件 | 限度額 |
|---|---|---|
| ア | 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降(注釈2):140,100円> |
| イ | 600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降(注釈2):93,000円> |
| ウ | 210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降(注釈2):44,400円> |
| エ | 210万円以下 |
57,600円 <4回目以降(注釈2):44,400円> |
| オ | 住民税非課税 |
35,400円 <4回目以降(注釈2):24,600円> |
- (注釈1)所得とは国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
- (注釈2)4回目以降…診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降である場合
世帯の医療費を合算できます
同じ月に、同じ世帯の人(共に70歳未満の人)が受診し、病院ごとにそれぞれ21,000円以上の一部負担金を支払ったとき、それらの一部負担金を合算し、その合算額が上記の「自己負担限度額」を超えたとき、その超えた分について高額療養費として支給します。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
70歳以上75歳未満の人は、個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。
(平成30年8月から)
| 所得区分 |
個人単位 (外来)のみ |
世帯単位 (外来+入院) |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降(注釈):140,100円) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (4回目以降(注釈):140,100円) |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降(注釈):93,000円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (4回目以降(注釈):93,000円) |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降(注釈):44,400円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降(注釈):44,400円) |
|
一般(課税所得145万円未満等) |
18,000円 (8月~翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降(注釈):44,400円) |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が町民税非課税の人。
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が町民税非課税でかつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人。
(注釈)4回目以降…診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降である場合
世帯の医療費を合算できます
同じ月に、同じ世帯の人(共に70歳以上の人)が受診した場合、それらの一部負担金を合算し、その合算額が上記の「自己負担限度額」を超えたとき、その超えた分について高額療養費として支給します(世帯単位で入院と外来があった場合は合算します)。
申請に必要なもの
- 被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等)
- 世帯主の銀行預金通帳
- 手続きする人の本人確認書類
- 世帯主と交付を希望する人のマイナンバー確認書類
時効
高額療養費の支給申請の時効は、医療機関へ支払後から起算して2年間です。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は1か月10,000円(注釈)までとなります。
(注釈)慢性腎不全で人工透析を要する、70歳未満の所得区分ア・イの人については、自己負担額は1か月20,000円までです。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
第三者行為(交通事故等)による届出
交通事故にあったとき
交通事故で第三者(加害者)から傷害を受けた場合は、原則として第三者(加害者)が治療費を全額負担することになります。
そのため、国保で治療を受けた場合には、直ちに役場の窓口で被害者が届出(第三者行為による被害届)をしていただく必要があります。法令により届出義務があります。
この手続きにより、国保が一時的に第三者(加害者)に代わって医療費を立て替え、後に国保が第三者(加害者)に請求します。
届出に必要なもの
- 交通事故証明書(警察で取得してください)
第三者行為による被害届 (PDFファイル: 120.4KB)
- 被保険者資格を確認できるもの(資格確認書等)
- 印鑑(認め印)
交通事故以外の傷病にあったとき
交通事故以外で第三者(加害者)から傷病を受けた場合でも、保険証を使った場合は上記と同様に被害届等の提出が必要になります。
例としては、次のような行為です。
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬に噛まれた
- スキー中の衝突
- 外食での食中毒 など
国保の給付が受けられない場合
次のような原因による傷病は、国保からの給付が受けられず、全額自己負担になる場合があります。
- 自身の犯罪行為による傷病(飲酒運転、無免許運転等)
- 故意による傷病(自殺未遂、薬物中毒等)
- 通勤中又は業務上の傷病 労災保険からの給付になります
示談
第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、治療中に示談をしてしまうと、国保から第三者(加害者)に医療費を請求できなくなります。
そのため、示談後に症状が悪化した場合でも、国保からの給付ができなくなり、事故の治療費は全額自己負担していただくことになるため、示談をする場合は事故治療の終了又は症状の固定後に行う必要があります。
第三者行為に関するご相談
その他、ご不明な点がある場合は、役場の窓口や加入されている損保会社へご相談ください。
また、下記の国保連合会のホームページに記載のある「交通事故に関する無料相談」もご利用ください。
詳しくは、住民保険課(役場内線170番)まで
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2508
ファックス:0745-77-6671

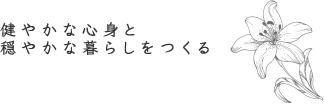
更新日:2025年07月01日
公開日:2022年03月28日