【令和7年度】定額減税にかかる調整給付金(不足額給付)について
令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)は速やかに支給するという観点から、令和5年中の所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出、給付を行いました。
今回の調整給付金(不足額給付分)は令和6年分所得税額及び定額減税可能額が確定した結果、本来支給すべき調整給付金の額が調整給付金(当初支給分)の額を上回ったかたに対し、追加で支給する給付金です。
対象となるかたには、令和7年8月上旬より、順次支給の確認書を送付しますので、内容を確認し必要事項を記入のうえ、申請期限までに確認書及び必要書類を返送してください。
※対象条件を満たすのに確認書が届かない場合は、下記問い合わせ先まで連絡をお願いします。
支給対象者及び支給額
以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当するかたが対象です。
ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度個人住民税に係る合計所得金額がどちらも1,805万円を超えるかたは対象外です。
【不足額給付1】
以下の(1)(2)の両方に当てはまるかたが対象です。
(1)令和7年度個人住民税が上牧町から課税されている
※(1)は以下のいずれかに当てはまるかたを指します。
・令和7年1月1日時点で上牧町に住所を有するかた(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、上牧町以外の自治体から令和7年度個人住民税を課税されているかたを除く)
・令和7年1月1日時点で上牧町の住民基本台帳に記録されていないが、同法に規定により上牧町から令和7年度個人住民税を課税されているかた
(2)「令和7年度調整給付金所要額」から「令和6年度調整給付金(当初給付分)算定額」を引いた額が0円より大きい。
※「令和7年度調整給付金所要額」とは、令和6年分所得税額から定額減税しきれなかった額(令和7年に入手可能な課税情報をもとに算定)と、令和6年度個人住民税から定額減税しきれなかった額の合計額です。
※「令和6年度調整給付金(当初給付分)算定額」とは、令和6年に実施された「定額減税に係る調整給付金」の算定額です。
具体的な例(対象となる可能性があるかた)
・令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことにより、
「令和7年度調整給付金所要額」>「令和6年度調整給付金(当初給付分)算定額」
となったかた。
・子どもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「令和7年度調整給付金所要額」>「令和6年度調整給付金(当初給付分)算定額」
となったかた。
支給額
「支給額」=「令和7年度調整給付金所要額(以下の1と2を合計し、1万円単位で切り上げた額)」-「令和6年度調整給付金(当初給付分)算定額」
1.「所得税分控除不足額」=「定額減税可能額(3万円×減税対象人数)」-「令和6年分所得税額(定額減税前)」
2.「個人住民税控除不足額」=「定額減税可能額(1万円×減税対象人数)」-「令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)」
※所得税分控除不足額は、令和6年中所得等に基づき算定します。(令和6年分確定申告書、令和6年分給与支払報告書、令和6年分公的年金等支払報告書などから算定します)
※個人住民税控除不足額は、令和5年中所得等に基づき算定します。(税額の修正や扶養是正等がない場合、当初調整給付時点から変更はありません。)
※減税対象人数について
・本人、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の人数です。
・国外居住者は含みません。
・所得税分控除不足額の減税対象人数は令和6年分所得税、個人住民税控除不足額の減税対象人数は令和6年度個人住民税における扶養親族等の状況による人数です。
・控除対象配偶者ではない同一生計配偶者は、所得税分控除不足額の減税対象人数には含み、個人住民税控除不足額の減税対象人数には含みません。
【不足額給付2】
以下の(1)~(3)すべてに当てはまるかたが対象です。
(1)令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がどちらも0円のかた
(2)税制度上、「控除対象配偶者」と「扶養親族」のどちらにもなることができないかた
※以下のいずれかに当てはまるかたを指します。
・青色事業専従者または事業専従者(白色)
・令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分住民税に係る合計所得金額がどちらも48万円を超えているかた
(3)低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員ではないかた
※低所得者世帯向け給付とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
具体的な例(対象となる可能性があるかた)
・青色事業専従者・事業専従者(白色)
(例)個人事業主の自営業などを手伝う青色事業専従者または事業専従者(白色)のうち、ご自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・個人住民税ともに課税されない)かたで、世帯内に課税者がいるため低所得世帯向け給付金の対象にならなかったかた。
・合計所得金額48万円超のかた
(例)合計所得金額が48万円を超えるかたのうち、所得控除や本人の状況等により所得税・個人住民税ともに課税されず、本人としても扶養親族等としても定額減税の対象ではないかたで、世帯内に課税者がいるため低所得世帯向け給付金の対象にならなかったかた。
支給額
原則4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)
※令和6年1月1日時点で国内のいずれの自治体の住民基本台帳にも登録がないかたは、個人住民税分が0円となり、合計3万円となります。
支給日
確認書を返送された方から順に支給日を決定し、個別に通知します。
※集中して申請があった場合は遅れる可能性があります。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)の消印まで有効
※期限までに申請されない場合は、支給できません。
この記事に関するお問い合わせ先
上牧町給付金・定額減税一体支援給付金窓口(役場1階)
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-71-7775
午前9時から午後5時(土、日、祝日を除く)

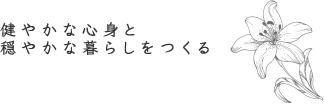
更新日:2025年08月05日
公開日:2025年08月05日